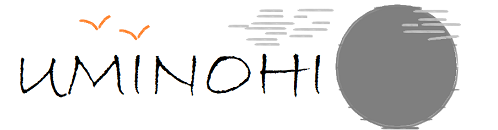結露対策 ー 布団の下
布団が濡れている・・・
布団が びちょびちょ・・・
そんな経験ってありませんか?

これはほんの少し前、冬の始まり頃に兄が家に泊まって帰った後のこと。
いつも自分が使っている布団のセット(厳密に言えば敷いているものはマットレス)を兄に貸していたので、それを自分の部屋に引き上げようと布団をあげた時、手には冷たい嫌な感触。
びちょっ
・・・いやーまさかね。
マットレスを裏返してその表面を撫でます。
びちょびちょびちょびちょ
・・・ははっ。完全に濡れています。新品のバスタオルを初めて使った時のような感じです。
うちの兄は大の汗っかき。
以前もっと暑い季節に兄が泊まった際には
「ごめんやけどめっちゃ汗かいてるから」
と言われて布団がびちゃびちゃだったことがありました。
今回もまたそれかな?と一瞬思いましたが今回の季節は冬。
そして私が住んでいる家は築50年の長屋の賃貸です・・・。
断熱?気密??なにそれ???(笑)
とまあとにかく断熱・気密など、まっったく、毛ほども、考えられていない家なので冬はめちゃくちゃ寒く、兄は寝るときに暖房をつけていなかったはずなのでさすがに汗とは考えにくい。
さらに兄からも今回は「ごめんやけどめっちゃ汗かいてるから」と注意は受けていません。
汗っかきの兄の体質のせいではないとなると考えられる原因はただ一つ。
「結露」です。
結露とは?
あらためて説明するまでもないかもしれませんが、結露とはどういった現象かについて少し触れておきます。

空気中には水分が含まれていますが、空気が含むことができる水分量は温度で決まります。
温度が高くなるとそのなかに含むことができる水分を多くなり、
温度が低くなるとそれが少なくなります。
ということは、
水分を多く含む温度の高い空気がどんどんと冷やされていくと、最後には水分があふれるということです。
そしてあふれた水分が物の表面で水滴になって現れる現象のことを「結露」と言います。
結露の例としては、夏の冷たい飲み物が入ったガラスコップ。
定番ですね。
これは夏の蒸し暑い空気が冷たい飲み物で冷えたガラスコップ表面に近づくにつれて冷やされることで起きます。
そして私としてはこれが重要。
結露は、
建物の壁の中や壁の表面でも起きます。
結露の対策とは?
結露という現象がどういう原理で起きるのかが分かれば対策もとれるというもの。
まずは結露が起きる条件を整理しましょう。
- 暖かく湿った空気があること
- 冷たい表面があること
- 暖かく湿った空気が冷たい表面にとどまること
以上の3つが結露の条件となります。

つまりこれらの条件のいずれかを成立させなければ、
結露はしない
ということです。
(3つの結露条件についてわかりやすさを優先して、暖かい、湿った、冷たい、といった抽象的な表現を使っていますが、実際には普通の感覚では冷たいと言われる10℃の空気でも湿度が80%くらいあれば、それが3℃のより冷たい表面に触れれば結露します。
どれくらいの温湿度の空気がどれくらい冷たい表面に触れると結露するのかを詳しく知りたいかたは、「湿り空気線図」という少し複雑な図の使い方を理解できればそれを簡単に知ることができるようになりますのでそちらをどうぞ。)
実際にした結露対策
布団が濡れている原因が汗ではなく結露であるということは、つまり汗っかきでない自分も同じことが起きる可能性が高いということ!
とはいえ何事も確認してみないと気が済まない性質なので、同じ布団のセットで寝てみることにしました。
(実は昨年まで自分は和室の畳敷きの部屋で寝ていたため布団の下が結露しているという現象には出会っていませんでした。)
翌日の朝、室温は7℃・・・。
7℃っ!?
とにかくバカみたいな室温は見なかったことにし、さっそく布団といいますかマットレスを裏返して確認してみます。
びちょっ
・・・予想通りばっちり結露しています。
結果としては悪いはずなのですが、なぜか少しうれしい自分。
理由は実験した結果が自分の予想通りだったから(笑)。
ということで、実際に結露対策をとっていくことにします。
御座マットの使用
まず一つ目の対策として、「御座マット」を敷くことにしました。

一つ目の効果として、マットレスの裏面が直接クッションフロアの冷たい表面に密着することを防ぎます。
こうすることで最低でも結露する場所がマットレス裏面ではなく、御座マット裏面になることが期待できます。
二つ目の効果として、御座によって多少なりとも空気の入れ替わるすき間ができ、暖かく湿った空気が冷たい表面にとどまることを防ぎます。
結露の3条件の中の「暖かく湿った空気が冷たい表面にとどまること」のとどまるという部分の対策ということで、これで結露の発生自体の対策が期待されます。
・・・正直に言います、結露対策としてはかなり弱いです。
もう一つ考えていた対策が「すのこ」。
こちらは御座マットよりさらにマットレスとクッションフロアの距離が離れ、空気の入れ替わりもかなり期待できます。
それではなぜ御座マットを選んだのか。
・・・いや、だってすのこって邪魔じゃないですかー。
布団をあげた後はただの邪魔でしかなくて壁にでも立て掛けておくしかないし。
その点、御座マットならそのまま敷いててもインテリアとして問題ない。
ええ、つまり部屋にもともと敷物もなかったし結露対策にもなったらいいな~というただの願望からの選択です(笑)。
さっそくホームセンターで買ってきた御座マットを下に敷き布団をセットして実験をしていきます。
翌日の朝、室温は8℃。
・・・もう何も言うまい。
マットレスを裏返して結露しているかどうか確認します。
さらっ
期待した通りマットレス裏面では結露していません。
それでは本命の御座マット裏面を確認しましょう。御座マットを裏返して手で撫でます。
びちょっ
・・・ですよねー。
やはりマットレスが濡れることを防ぐという対策にはなりますが、根本的な結露対策として「御座マット」は不十分でした。
それでは別の手を考えましょう。
アルミシートの使用
次にとった対策は、「アルミシート」を使用すること。
最近は100均でも売っているアルミシート、薄い白いスポンジみたいなものの片面にアルミが貼り付けられている製品です。

「アルミマット」という製品もあり、そちらのほうがスポンジ部分が分厚くよりふさわしいと思いますが値段は100均アルミシートの数倍。
今回は実験でもあるので100均で買えるアルミシート一択です。
アルミシートで期待している効果は、アルミ部分が水分の行き来を遮断すること。
水分の行き来を遮断することで、結露の3条件の中の「暖かく湿った空気が冷たい表面にとどまること」という条件を成立させないことが今回の目的になります。
どういうことかという説明をするためにはこれまでマットレスの下で結露が発生していた流れを理解していないといけません。
- マットレスの上に寝ている人の体(体温36℃)から水分が発生している。
- 体温がマットレスに伝わり中の温度が上がると同時に体から発生した水分がマットレスの中に入る。
- マットレスが(熱と水分を吸収しながらも)下まで熱と水分を通す。(つまりマットレス内部には暖かく湿った空気が存在する。)
- マットレス内部の暖かく湿った空気が室温7℃のクッションフロア表面に到達する。
- 結露発生!!!
これまではこのような流れで結露が発生していましたが、この流れをアルミシートで止めます。
それにはアルミシートをどこに設置するかということも重要です。
さてそれはどこでしょうか?
正解は・・・マットレスの上です。
上で言うところの❶と❷の間で流れを止めるということになります。
「体温がマットレスに伝わり中の温度が上がると同時に体から発生した水分がマットレスの中に入る。」という部分。
ここで水分がマットレスの中に入ることをアルミシートで止めることができれば、
クッションフロア表面に到達する空気は暖かく乾いた空気となり、
結露の条件が成立しなくなるのです。

考察
マットレスの下にアルミシートを敷いた場合はどうなるでしょうか。
上で言うところの❸と❹の間で流れを止めるということです。
この場合、❸の時点でマットレスの下部までは暖かく湿った空気が到達しています。
ここでアルミシートによる水分の遮断を行った場合、その先に水分が到達しないのでクッションフロア表面に結露は発生しません。
ただし、アルミシートの温度は冷たいクッションフロアの温度の影響を受けてかなり冷えている状態になります。
つまり結局はアルミシートとマットレスの間で結露が発生してマットレス裏面が濡れる結果となります。
理論上では結露対策として成立しているとわかりましたので、あとは実践あるのみ。
まずマットレスを敷き、その上にアルミシートを広げてからその上にシーツを敷きます。
このシーツは寝心地の確保とともに多少なりとも体から発生した水分を吸湿してもらう目的です。
さっそく上に寝てみます。
がさがさっ、ガサガサッ、がさっガサッ。
・・・動くたびにがさがさとアルミシートがこすれるときの音がします。
アルミシートの上にシーツを敷いているので寝られないほどではありませんが、あまり心地のいいものではありません。
まあ実験なので今回はこれで我慢しますが、基本はアルミマットを推奨です。
(後日アルミマットも使ってみましたが、アルミマットの硬さがマットレスの寝心地を損ねました。その点でアルミシートのほうがよいかもしれません。)
ということで問題がないわけではありませんでしたが実験の準備は完了。
がさがさと音を立てながら眠りにつきました。
翌日の朝、室温は7℃。
実験のためには条件はできるだけ同じが良いんだ!と自分に言い聞かせながらいつも通りマットレスを裏返します。
マットレスの裏面を手で撫でると、
さらっ
ばっちりです。マットレスに結露は発生していません。
念のためアルミシートの表面も確認しますが、
どこにも結露は発生していませんでした。
建物の結露対策との共通点
今回なぜ自分が建物や家具に関係のなさそうなブログを書いているのかというと、布団の結露対策と建物の結露対策は共通していると感じたからです。
建物では壁の中や壁の表面に結露が発生してしまってはなりません。
結露からカビが発生すると病気になってしまったり、
断熱材が濡れると性能が落ちてしまったり、
建物の構造体が湿気を含んだままだと耐久性が低下してしまったり。
色々な悪影響が発生するかもしれないからです。
そうならないために建物では、
壁の中に防湿シートを施工して水分が冷たい表面まで伝わらないようにしたり、
反対に水分を通しやすくして室内外に水分を排出しやすくしたり、
通気層を設けてそこから水分を排出してしまったり、
さまざまな考え方で結露の対策を施します。
今回のアルミシートでの対策というのは、建物で言うところの防湿シートを施工することと考え方は同じですね。
水分が冷たい表面に到達するまでにブロックしてしまおうということ。
今回は布団の下の結露対策ということでお話をしましたが、結露対策の考え方は建物でも同じ。
結露の3条件のうちのどれかをいかにして成立させないようにするか。
あなたが自分のおうちを建てるときには、こうした観点で壁に使われている材料などを確認してみるのも大事ですよ。